![]()
![]()
全ての記事
-
2023.08.24
「新しい戦前なのか」ーーこの夏の宿題③
1学期の終業式で「新しい戦前にしてはいけない、この夏は戦争、平和を考える夏にしてほしい」と生徒たちに話をしたのですが、そもそもはテレビでおなじみのタモリさんが昨年末、テレビ番組で「2023年はどういう年になると思うか」と尋ねられ、「新しい戦前になるのではないか」と答えたという話がネットなどで話題になったことがきっかけでもありました。この夏、あちこちで「新しい戦前」という言葉を目にします。
8月3日毎日新聞朝刊のオピニオン面「司馬遼太郎氏生誕100年」特集で、片山杜秀さん(慶応大学教授)が、日露戦争を描いた司馬作品「坂の上の雲」にふれ、「今や「新しい戦前」という言葉が聞かれるようになった。(略)日本は「戦前」を受け入れるモードに入っている。まさに「危機の時代」だ。「坂の上の雲」を「危機の時代の小説」として読む現代的な意義はそこにある」と語っています。
この夏の宿題①、②で紹介した加藤陽子さんが作家の奥泉光さんと対談した『この国の戦争--太平洋戦争をどう読むか』(河出新書、2022年)で奥泉さんはこう書いています。
「永遠に戦争のない世界。日本国憲法にも響くこの理想は、人類が苦難の末に獲得した理念であり、失ってはならないが、日本が新たな「戦前」のただなかにあるのはまちがいなく、「戦後」を継続するためにも、「戦前」体制の整備は喫緊の課題となるだろう。(中略)いま求められるべきは、昭和とは違う「戦前」、戦争をしないための「戦前」の構築である」
片山さんは同じ毎日新聞の記事で語っています。
「明治はある意味、戦争の期間を除けば常に「戦前」だった。「坂の上の雲」は、明治国家が戦争に備える「戦前小説」としても読めるのではないか」としたうえで、「日本が上り坂の時代に、どう外交をして、どう軍備を備えて、それでかろうじて勝てたということを学べば、下り坂の今の日本に、戦争ができるなんて思えないはずだ」加藤さんは『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮文庫)で中高校生に語りかけます。戦前、1930年代から何を学ぶかについて「国民の正当な要求を実現しうるシステムが機能不全に陥ると、国民に、本来見てはならない夢を疑似的に見せることで国民の支持を獲得しようとする政治勢力が現れないとも限らないとの危惧であり教訓です」とし、「戦前期の陸軍のような政治勢力が再び現れるかもしれないなどというつもりは全くありません」としながらも、現代における政治システムの機能不全の例として衆議院議員選挙制度と投票率の低迷をあげ、「若い人々には、自らが国民の希望の星だとの自覚を持ち、理系も文系も区別なく、必死になって歴史、とくに日本近現代史を勉強してもらいたいものです」と呼びかけています。
-
2023.08.23
「新しい戦前なのか」ーーこの夏の宿題②
1930年代の外交・軍事を専門とされている加藤陽子さんの著作『戦争の日本近現代史 征韓論から太平洋戦争まで』(講談社現代新書、2002年)では、日清戦争が終わり、続く日露戦争の開戦にいたるまでの時期については、また違った状況があったと説明しています。
「日本政府の側が日露開戦へとキャンペーンのごときものを張って、国民を積極的に開戦へと導いたあとはみられません」「国際的な環境が、戦争への道を自然に導くものであったことが指摘できます」
そして「日露戦争をいつ始めるかという決定は、軍備完整の状況、戦費調達の見込み、国際環境などから周到になされていたことがわかります」とも。その後の第一次世界大戦、満州事変、日中戦争と論を進めていきます。
詳しくはぜひ読んでいただきたいのですが、「満州事変の前後ほど、国民全体の事変への受け止め方が、関東軍の発する言葉と一体化していた時期はなかったように思います」とし、「日本を正とし、中国を悪とする、二分法の論理」「条約=法を守る日本、法を守らない中国」「戦争をおこなうためのエネルギーの供給源は、まさに国際法にのっとって正しく行動してきた者が不当な扱いを受けたという、きわめて強い怒りの感情でした」などとあります。あれあれ、何やら日清戦争の時の対比の論理とよく似ていませんか。
その日中戦争は宣戦布告のない「戦争」なので、「賠償金も、新たな土地の割譲も望めない戦争に、どうやって国民の士気を集中させればよいのでしょうか。政府はここで深いジレンマに立たされることになります」。
そして「国民が心から受けとめられる戦争目的を、どのように設定していったのでしょうか」と問いを投げかけ、中国の民族主義の否定、東アジアの民族を超えた地域的連帯の必要性を訴え、中国の国民政府を援助する英米の帝国主義国家も打倒されねばならないという、あのいまわしいスローガンの数々がでてくるわけです。
『戦争の日本近現代史 征韓論から太平洋戦争まで』は新書ですが内容は相当濃いです。内外の文献の引用も豊富で確かなものと感じます。ある程度の近現代史の基礎知識がないとと思わないでもありませんが、重要な視点が随所に出てきます。念のためですが、この著作は、国民が戦争をやむをえないと受け止め、あるいは積極的に求めたりするようになる何かがあったはずという問題意識で書かれているので、それぞれの戦争での具体的な戦闘内容や市民がどのように犠牲になったのかなどは、あまり書かれていません。
加藤さんのもう一つの著作を
『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮文庫、2016年、もとは朝日新聞出版2009年)加藤さんが神奈川県内の私立中高一貫校の歴史部の生徒に、太平洋戦争にいたる近現代史について「授業」をした、その記録です。以下、『選んだ』と書きます。
実はこちらを先に読んで、その後に『戦争の日本近現代史 征韓論から太平洋戦争まで』(以下『近現代史』とします)を読んだのだと思うのですが、今回、2冊を続けて読み返してみて、『選んだ』の内容は『近現代史』にそったものでした。タイトルの「それでも日本人は戦争を選んだ」には少し疑問も持っていたのですが、『近現代史』の主題である「為政者と国民」という切り口からすると、タイトルは加藤さんの視点そのものずばりということが確認でき、すこしほっとしました。
歴史部の生徒の反応も素晴らしいですし、正直高校生にしては出来すぎ、と思わないでもないですが、加藤さんが『近現代史』で書いた内容を高校生にもわかりやすく授業をしていることに、ただただ敬服しました。高校生相手だから難しいところは避けて、ということはなく、内容は『近現代史』とそん色のないものです。
加藤さんの授業は、2001年9月にアメリカで起きた同時多発テロから始まります。
このテロに対するアメリカの「戦争」について加藤さんは「アメリカの感覚は、戦争の相手を打ち負かすという感覚よりは、国内社会の法を犯した邪悪な犯罪者を取り締まる、というスタンスだったように思う」「そうなると、戦いの相手を、戦争の相手、当事者として認めないような感覚に陥っていくのではないでしょうか」と問いかけ、「日中戦争期の日本が、これは戦争ではないとして、戦いの相手を認めない感覚を持っていたことに気づいていただければよいのです」と続けます。「ある意味2001年時点のアメリカと、1937年時点の日本とが、同じ感覚で目の前の戦争を見ている」と生徒たちをひきつけます。「歴史の面白さの神髄は、このような比較と相対化にあるといえます」とも。現代と歴史を結び付けて考える大事な視点を中高校生に教えています。
このくだりを読んでどうしても考えてしまうのが、ロシアのウクライナ侵攻です。宣戦布告をしたからといって戦争を正当化するつもりは毛頭ありませんが、ロシアは宣戦布告すらなくウクライナに侵攻し、その行為を正当化するためでしょう、特殊軍事作戦と称しています。
-
2023.08.22
「新しい戦前なのか」ーーこの夏の宿題①
この夏も、広島、長崎で原爆投下による犠牲者を悼み、太平洋戦争の終結の日を迎えました。1学期終業式で生徒のみなさんには、夏は戦争について、平和について考えてほしいという話をしました。そこでは、テレビでもおなじみのタモリさんの、今年が新しい戦前になるかもしれない、という発言を紹介しました。保護者のみなさまにお配りしている「東野便り2号」でもとりあげました。
もちろん「新しい戦前」にしてはいけないと話し、戦争について、平和について考えらもらうことを、いわば夏休みの「宿題」としたのですが、自分自身も改めてこのことに向き合うために、太平洋戦争のまさに戦前、1930年代の外交・軍事を専門とされている加藤陽子さんの著作を再読しました。
『戦争の日本近現代史 征韓論から太平洋戦争まで』(講談社現代新書、2002年)
『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮文庫、2016年、もとは朝日新聞出版2009年)『戦争の日本近現代史 征韓論から太平洋戦争まで』(以下『戦争の』と略します)では、為政者や国民が、いかなる歴史的経緯と論理の筋道によって、だから戦争にうったえなければならない、だから戦争はやむをえないという感覚までを持つようになったのか、そういった国民の視覚や観点や感覚をかたちづくった論理とは何なのかという切り口から日本の近代を振り返ってみる、という主題が提示されます。
ここで注意したいのは「国民」が入っていることです。単純に軍人や一部の政治家が危機を煽り、国民はそれに引きずられて戦争に「巻き込まれていった」ということではなく、国民も「戦争をやむをえないと受け止め」、「あるいは積極的に求めたりするようになる」何かがあったはず、という問題意識です。
近現代史とあるように、幕末にまでさかのぼります。幕末の攘夷論が大きな力となってできたはずの明治新政府がその「攘夷」、つまり外国を排撃することができないという「矛盾」あるいは「負の遺産」が、新政府に大胆な施策をとらせ、人々のあいだに対外的危機に敏感な近代的政治意識を急速に浸透させていった、というところから始まります。
例えば自由民権運動の一般的な印象からすると、いわゆる民権派は平和主義者と考えがちですが、「日本の自由民権運動は、最初から国権論的な動機づけをもっていたがゆえに、広く支持を獲得できたといえるでしょう」とあり、まずここではっとさせられます。加藤さんは民権派の主張が掲載された新聞などを参照しながら「列強に対峙するための軍拡については、為政者と民権派のあいだに、基本的な対立は生じようはなかったはずだ」ととらえています。
明治期の陸軍のリーダーだった山形有朋の、日本と朝鮮半島・中国大陸との関りでの戦略観には、伊藤博文が帝国憲法作成にあたって指導を受けたウィーン大学のシュタイン教授の影響が非常に強いことに注意を促します。開設された国会では軍事費を増強させたい政府と民権派が激しく対立したように従来語られてきましたが、「軍事費そのものをめぐる部分では、基本的な対立がなかったとみなせます。日清戦争を軍事的に可能とする軍事予算は、着実に獲得されてゆきました」
その日清戦争、軍事戦略的な論点だけでなく、「為政者や国民にとって避けられない戦争だと自覚されるには、いま一歩別の媒介物が必要であった」と、冒頭であげた本書の主題による問いかけがでてきます。そして加藤さんは「内政改革に熱心な日本、それを拒絶する清国という、きわめて単純な対比の論理が加わりました。これは、国民が戦争を理解する上で、軍事戦略論から説く利益線論よりは、有力な論理の筋道を提供していったはず」ととらえます。(軍事戦略論から説く利益線論は山形有朋が提案した考え方です)
そして「文明と野蛮の戦争という、非常にわかりやすい構図を明示された国民は、近代となって初めての本格的な対外戦争を熱心に受け入れ」たのです。(つづく)
「東野便り2号」はこちらから。PDFファイルです
-
2023.08.17
明日18日は登校日ですーー満開のひまわりが迎えます
明日18日は生徒の登校日です。朝、普段通りの始業となります。
太鼓橋からFVB(Future View Base)に向かう通路脇に植えられた1000本のひまわりが満開となっています。

後方の赤い屋根の建物が自習などで活用する多目的施設「FVB(Future View Base)」です
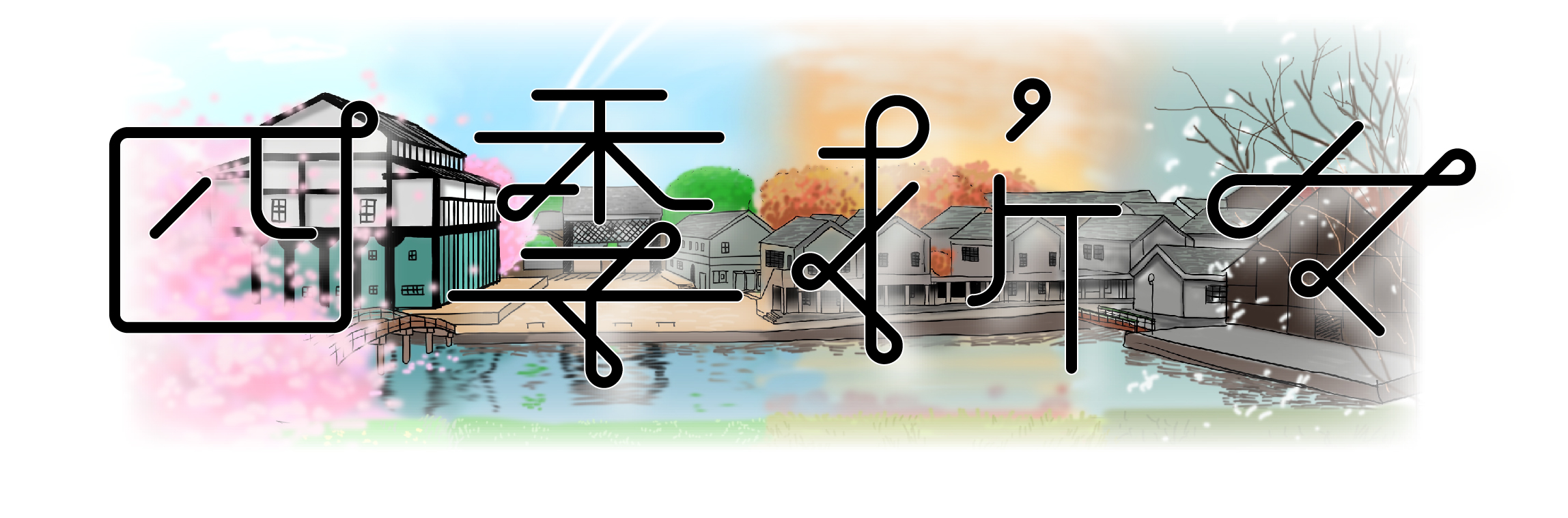
-
2023.08.10
吹奏楽部が西関東大会へ
「埼玉県吹奏楽コンクール高等学校Bの部」県大会が8日、さいたま市文化センターで行われ、東野高校吹奏楽部は金賞に輝き、西関東大会に出場することになりました。おめでとうございます。
くわしくは、クラブブログをどうぞ。こちらから
私のいる部屋は吹奏楽部が主な練習場所としている音楽室から少し離れていて、「生」の音を聴くことがなかなかできないのですが、パート練習で教室から漏れ聴こえてくる音色に、ああ学校だなあと心温まる思いがします。音楽があるキャンパスっていいなといつも感じています。
お休みをいただきます
さて8月17日まで登下校用のスクールバスは運休で事務室は閉室、学校の代表電話も留守番電話になります。
個人的にもお休みをいただくので、このブログも1週間ほど、お休みをいただきます。
-
2023.08.10
「新曲」との出会い そして祈り
さだまさしさんの作品『甲子園』は、さださん関連の本をきっかけに、発表の1983年から40年後の今年、私にとっての「新曲」となりました。この思わぬところでの出会いという曲が、さださんについてはまだあるのです。そのひとつは『償い』です。
「裁判官の爆笑お言葉集」(長嶺超輝、幻冬舎新書、2023年)2007年初版、購入した版は第31刷という大ベストセラーです。「爆笑」となっていますが、法廷で判決文を淡々と読み上げるだけと思われる裁判官が被告に向かって結構生々しいコメントや意見を発言している、そんな事例を集めた本です。その冒頭に紹介されているのが、裁判官の「君たちは、さだまさしの償いという唄を聴いたことがあるだろうか」という説諭です。
『償い』は、交通事故の加害者が毎月の給料を割いて被害者の遺族にお金を送りつづけたという内容の歌で、裁判官は傷害致死罪で起訴された少年2人の被告に反省の様子が見られないことからこの問いかけをしたのです。こう続けます。
「この唄の、せめて歌詞だけでも読めば、なぜ君たちの反省の弁が、人の心を打たないかわかるだろう」この裁判、説諭は2002年のことで、新聞でも異例のこととして取り上げられました。
さださんの1982年発表のソロ7枚目『夢の轍』(ゆめのわだち)に収められた曲です。しつこいようですが就職したばかりの時期でこの『償い』も発表時には聴いていません。この判決のニュースで「さだまさしにそんな曲があったんだ」と知ったのです。実際にあった話を歌にしたそうで、今でも聴くと胸がしめつけられます。
もう1曲は『風に立つライオン』です。
アフリカ・ケニアで医療にあたる青年医師がモデルの作品、日本に残した恋人から結婚を知らされる手紙への返信という形で、アフリカでのくらしのこと、患者とのふれあい、日本への思いなどを語るという内容です。楽曲は1987年発表。
この曲との出会いは1992年、茨城県内の塾で中学3年生の女子生徒に教えてもらいました。新聞社で学習塾の取材をしている時で、この塾では休憩時間にみなで音楽を聴くのです。クラシックやポピュラー、民謡、黒人霊歌など音楽のジャンルは問わず、塾長が毎回選曲をします。女子生徒にこれまで一番印象に残った曲を尋ねると返ってきたのが『風に立つライオン』でした。その時の新聞記事にはこうあります。
女子生徒は「自分の好きなことをしようという青年、彼女と離れたことは可哀そうだが、女の人も男の人の人生を見守っていてあげて偉い」と解説してくれました。
この時はすぐにCDを購入して聴いたと思います。
その後さださんは被災地などでチャリティコンサートを積極的に行うのですが、へき地医療や災害現場での復旧活動にあたる人を支援する組織や人たちを支援する団体をつくります。その団体名が「風に立つライオン基金」。
さださんにはすばらしい曲がたくさんありますが、いろいろな意味で、『風に立つライオン』はさださんの代表作の一つだと思います。思わぬところではありましたが、出会えてよかった楽曲の一つです。
「風に立つライオン基金」の公式ホームページはこちら
これも余談ですが・・・説諭で『償い』をとりあげた裁判官、『裁判官の爆笑お言葉集』でも説明されていますが、法律にのっとって淡々と進められるのが裁判、裁判官の個性が感じられる場面は少ない、いやむしろあってはいけないと多くの人が考えていると思います。私自身新聞記者をしていて法廷での取材経験はありますが、この本に出てくるような裁判官の「生の声」を聴いた記憶はありません。
でも裁判官だって、法廷での被告人の態度とかに一言いいたくなることは絶対にあるはず、それをずっと我慢しているのだろうと推測します。この本は、実はそうでない、裁判官の「生の声」が結構聞けるんだよ、ということをとりあげたことが新鮮だったのでしょう。
市民から選ばれた人が裁判官になる裁判員裁判制度が導入され、司法(裁判)を身近にしなければならないというのが近年の司法の使命の一つになっているなかで、裁判官が市民に届く言葉で語ることも重要になってきていると考える裁判官が増えているのかもしれません。考えすぎでしょうか。
「甲子園、野球の歌 その1」(8月8日)で、さださんの『甲子園』が収められているアルバム「風のおもかげ」についても書きました。改めてCDの歌詞カードめくっていたら『祈り』という曲にこんなくだりがありました。
「この町がかつて 燃え尽きた季節に / 私たちは誓った 繰り返すまじと」
さだまさしさんは長崎の出身です。きのう8月9日、長崎に原爆が投下され78年がたちました。
-
2023.08.10
甲子園、野球の歌 その2
さだまさしさんの作品『甲子園』のことを知り、すぐにその曲が収録されているCDアルバム「風のおもかげ」を購入しました。この1曲を聴くだけならネットでダウンロードできるし、その方が安価と若い人には笑われそうです。
CDどころかレコードから音楽にふれてきた世代としては、楽曲がパッケージ、ひとつの「かたまり」として表現される形を大事にしたい、こだわりたいと考えています。「アルバム」というのですから、どういうテーマ、コンセプトで曲を作り、あるいは選び、どういう順番で並べるのかというのも、ミュージシャンの「表現」なわけです。まことに年寄りのこだわりではありますが。
おかげで、アルバム「風のおもかげ」で『甲子園』以外にも魅力的な曲に出会えました。これって、ネット通販で必要な書籍をピンポイントで購入するのもやむを得ないものの、書店内を歩いて棚をながめることで思いもよらぬ本で出合える、ということと同じですね。
さださんが野球を題材にした曲には『二軍選手』という曲があります。
1989年発表のソロ14枚目『夢の吹く頃』に収録されています。カズレーザーさんも『うらさだ』(小学館文庫、2023年)で触れていますが、こちらは知っていました。
売れない歌手(僕)とプロ野球二軍選手(彼)との友情、二人とも飛躍(歌のヒット、1軍定着)のチャンスは生かすことができなかったが、僕は小さな酒場で歌い続けている、彼はバッティングピッチャーとして投げ続けている、歌が好きだから、野球が好きだから、といった内容です。こちらもスリーフィンガーのギターが主伴奏、『甲子園』に雰囲気は似た曲です。
さださんが尊敬し影響を受けたサイモンとガーファンクルの名曲「ボクサー」(1969年)を意識して作られた曲だと思います。まったくの余談ですが・・・『甲子園』の歌の舞台になっているのは喫茶店ですが、店内のテレビで野球中継を流しているわけです。最近の喫茶店ではちょっと考えられないので、若い人たちにはピンとこないかもしれませんね。
スポーツバーなどにサポーターが集まって観戦・応援することになぞらえたらとも思いましたが、こちらは積極的に「観る」、みんなで「観て盛り上がる」ことが主目的。
ところが喫茶店のテレビで流れる野球放送は「なんとなく見ている」「時々目に入る」ですね。見ない人もいるわけです。アルバム発表の1983年は昭和58年、昭和の終わりが近づいていました。
-
2023.08.08
甲子園、野球の歌 その1
高校野球、いわゆる夏の甲子園(全国選手権大会)の熱戦が続いています。広島カープ監督新井貴浩さんの球児たちへの素晴らしい応援メッセージについて紹介しましたが(6月20日付ブログ)、その後、思わぬきっかけで同じような視点で高校野球をとらえている歌に出会いました。タイトルはそのものずばり、さだまさしさんの『甲子園』です。
1983年発表された、さださんのオリジナルアルバム8枚目になる「風のおもかげ」に収められた1曲です。スリーフィンガー奏法(フォークギターの弾き方の一つです)のギターがメインの伴奏で軽快に歌われます。
著作権があるので詞(さださんは「詩」と表記するのですがここでは一般的な方で)をまるまる紹介することはしませんが、喫茶店のテレビで甲子園の試合が放送されている、その店での男女の会話、やりとりが描かれます。
「ホームラン」とテレビが叫ぶ(もちろん実際はアナウンサーが叫ぶのですが、こういう表現になるわけですね)のを受けて「また誰かの夢がこわれる音がする」。
「3000幾つの参加チームの中で たったの一度も負けないチームはひとつだけ」、各都道府県大会の出場校を合計するとこのくらいの数になる、そして甲子園に出場して優勝するのは当然ですが1チームしかないわけです。ちなみに今年の大会、全国の予選参加チーム数は3744校でチーム数は3486とのこと(学校数とチーム数が一致しないのは合同チームがあるためですね)。
「敗れて消えたチームも 負けた回数はたったの一度だけ」と続くところに、さださんの「敗者」へのまなざし、やさしさを感じるのですが、考えすぎでしょうか。
さださんはアルバムのライナーノーツ(作者自身の解説)で次のように書いています(抜粋します)。「優勝チームの校歌を聴くとき、ああこの子たちは今年の夏一度も負けなかったのだなあと奇跡でも見る思いになる」
「同時に、それ以外の、甲子園に来る事が出来なかったチームをふと思う。そうしていつも得体の知れない熱い思いに駆られてしまうのだ」さだまさしさんの曲は中学生からギターを弾き始めてから相当数聴いて、弾いてきました。ただ、このアルバム発表時はもう仕事についていたので音楽からは少し遠ざかり、このアルバムもこの曲「甲子園」も知りませんでした。それなりの年齢になってまたゆっくりと音楽を楽しむ余裕が出てきてから聴くのは結局、昔聴いていたロックでありフォークになってしまいます。さださんについてもベストアルバム的なものは購入して聴いてはいましたが、やはりそこではこの曲には出会えなかったのです。
長々と思い出話になりましたが、ではどこでこの『甲子園』を知ったかというと、つい先日読んだ『うらさだ』(小学館文庫、2023年)でした。筆者が「さだまさしとゆかいな仲間たち」とあるように、落語家の笑福亭鶴瓶さんやミュージシャンの高見沢俊彦さん(アルフィーのメンバー)、やはりミュージシャンで災害地でのボランティアコンサートなどを一緒にしている泉谷しげるさんら、さださんと交友がある人たちが、自由に「さだまさし」を語っているという内容です。
その中でカズレーザーさんがこの『甲子園』をとりあげていました。あの金髪で真っ赤な衣装の方です。さださんと交友があったことすら知らなかったのですが、思わぬところから新しい曲を知るきっかけに感謝しました。
こんな発見、出会いを用意してくれるから、本を読むことはやめられませんね。
カズレーザーさん、ネットで検索したら埼玉県加須市出身、熊谷高、同志社大卒だそう。埼玉の人だったんですね。
-
2023.08.07
「ひまわり」が咲き始めました
校内の池・太鼓橋を渡って多目的スペースFVB(Future View Base)に向かう通路脇の斜面に植えられた「ひまわり」の花が咲き始めました。
ウクライナ、ロシアの国の花でもある「ひまわり」。戦争について平和について考えるきっかけにしたいと昨年に続いて1000本の苗を植えました。
昨年とほぼ同時期の開花で、18日の生徒登校日のころには満開となりそうです。


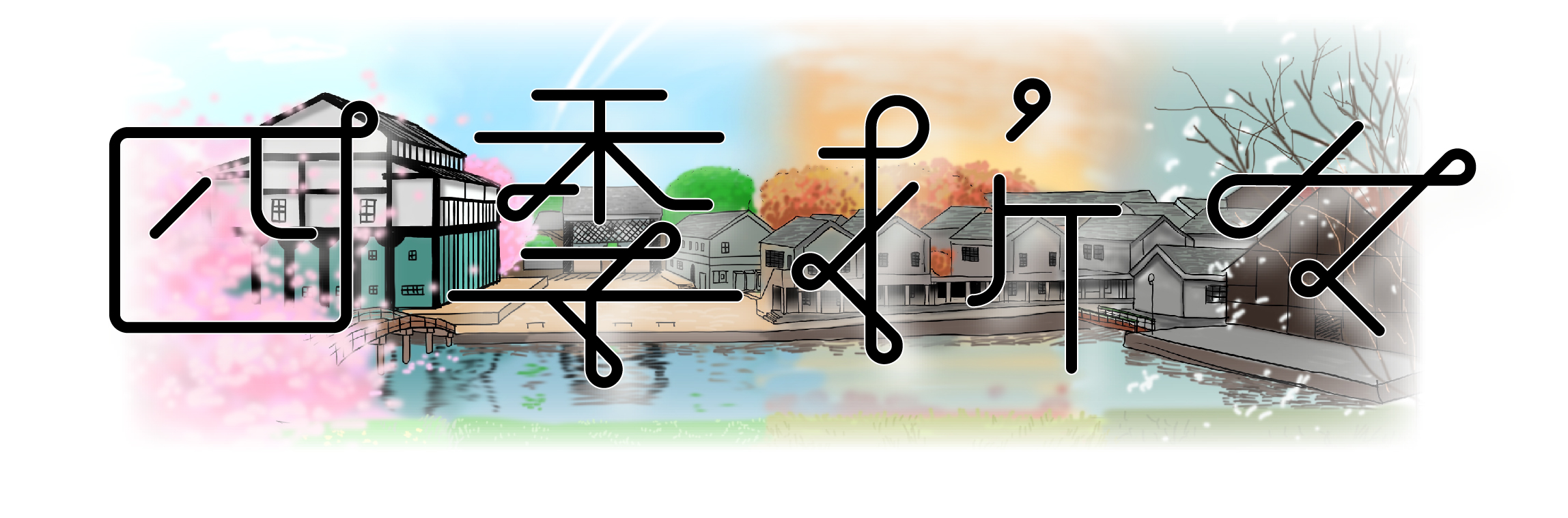
-
2023.08.07
「甲子園の土」と沖縄
開幕した高校野球、夏の甲子園大会で、選手たちが試合後に甲子園球場のグラウンドの土を集めて持ち帰ることが4年ぶりに認められ、テレビ中継や新聞でその様子が報じられています。毎年、おなじみの光景だったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大以降、チーム入れ替え時の接触を避け、また、入れ替を速やかに行うために控えるよう呼びかけられていたとのこと。
この甲子園の土については、1958年(昭和33年)夏の大会に沖縄勢として初めて出場した首里高校をめぐる話がよく知られています。とはいいつつ、今の高校生は知らないかもしれません。沖縄は今秋の本校修学旅行先の一つ、事前学習にもなりそうなのであえて取り上げます。
インターネットなどで検索すると、この話はすぐに見つけられると思いますが、今回の引用は以下によります。
『不滅の高校野球 下 栄光と感激のあと』(松尾俊治、ベースボールマガジン社、1984年)ちょっと古い本ですが、著者は毎日新聞の記者(大先輩です)、発行年からして「教材」「資料」として購入したのだと思います。
1958年の夏の大会は40回記念ということで、アメリカの統治下にあった沖縄の代表として首里高校が出場することになりました。初戦で敗れ試合後、グラウンドの土を袋に入れ持ち帰ろうとしたのですが、沖縄・那覇港でその土は検疫官によって没収され、海に捨てられてしまいます。土は植物検疫法に触れるという理由だったそうです。
今でも、多くの国で海外旅行で持ち込んではいけないものがありますよね。生物多様性の維持、外来種の入り込みを防ぐために動植物の輸入・持ち込みが禁じられます。この「土」もその例、沖縄は「外国」だったわけです。
この話を聞いた日本航空のスチュワーデスさんが、土がだめなら検疫に触れない石をと、甲子園の外野で拾い集めた数十個の小石を甲子園をかたどった形で箱に詰め、スチュワーデスのリレーで首里高校に届けられました。この石は、甲子園出場を記念して校内に設置された「友愛の碑」に埋め込まれています。
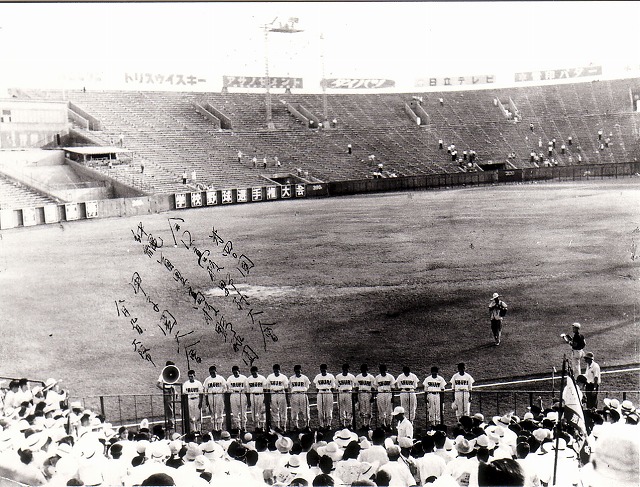
1958年第40回大会に出場した首里高校の選手たち。写真は「那覇市歴史博物館デジタルミュージアム」より。この首里高校の選手たちと甲子園の土については、沖縄の高校の先生が著した「高等学校 琉球・沖縄史」(新城俊昭、1998年第3刷)でも取り上げられています。同書では選手たちが砂を集めている写真も掲載されていますが、『那覇百年のあゆみ』(那覇市企画部市史編集室・編、1980年)によっているようです。
この1958年が沖縄県勢の初出場、甲子園初勝利は1963年(昭和38年)の夏の大会、同じ首里高校。初優勝は沖縄の本土復帰後の1999年(平成11年)春のセンバツ大会での沖縄尚学高です。
内閣府のホームページ「沖縄県民を熱狂させる野球」に、沖縄の高校野球が詳しく紹介されています。こちらその冒頭、こんなくだりがあります。
「沖縄とスポーツ」を語る上で、野球の存在は欠かせません。特に高校野球に対する熱は極めて高く、沖縄のチームが甲子園で試合をする時は、多くの県民が自宅や職場、ショッピングモールなどでテレビ中継に釘付けになります。その様子は、試合の最中に「道路から車がいなくなる」と言われるほどです。高校野球が一スポーツにとどまらず、一つの「文化」として地域に根付いているといっても過言ではないかもしれません。そんな大げさな、と思われるかもしれませんが、10年以上前の私的な経験です。
沖縄で児童生徒向けのニュース解説の催しを地元新聞社が主催。講師役のジャーナリストのアテンドをしました。その新聞社の人が、会場(ホール)が野球場と同一敷地内にあり、高校野球県大会の最終盤に差しかかっていた時期だったため、野球観戦による付近の交通渋滞が心配、そもそもみんな野球観たくてイベントに来ないのではないかと真顔で心配していたことが忘れられません。幸い、イベントは満席になりましたが。